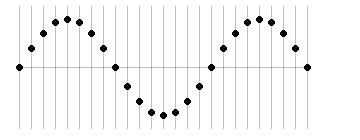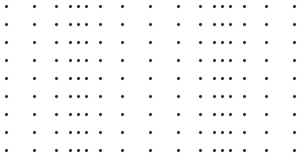最近流行りの(?)音響処理について考えていきたいと思います。
国内だけでもいくつかの個人・企業様が、「音響処理」という名の処理を施されていますが、その内容はほぼ極秘。そのため、音響処理の概要を説明し、その上で、その効果について考えていきましょう!
その前に「音響処理」は、ほぼ間違いなく金属の熱変性を利用した処理であることをご理解ください!
種類にもよりますが、金属は熱を加えたり、冷却したり、叩いたり、空気中に放置したりすることによって、その性質が大きく変化することがあります。熱処理だけでも「焼き入れ→固くなる」「焼き戻し→粘り強くなる」「焼きなまし→柔らかくする」「焼きならし→組織を均一化する」等の方法があり、さらに温度や冷却時間・方法によって細分化されます。
金属には、本来の金属元素以外にも様々な元素が微量に存在し、その種類や量によって、金属硬度に大きな影響を与えます。金属の熱処理において、もっとも分かりやすいのは「鉄」なので、それぞれの熱処理については、ネット上で調べてみてください(話が複雑になるため、ここではあえて割愛します)。
モノタロウさんのサイト(機械部品の熱処理・表面処理基礎講座 【通販モノタロウ】 (monotaro.com))、かなりわかりやすく勉強になりますよ!
金管楽器のほとんどのマウスピースは真鍮(黄銅)でできていますが、その熱変性は鉄とは異なります。真鍮は「銅」と「亜鉛」の合金で、炭素をほぼ含まないために、炭素原子が影響する鉄のような焼き入れや焼き戻しは、ほとんど関係はありません。詳しく調べてみるとわかりますが、「音響処理」と呼ばれる手法は、「焼きなまし(焼鈍)」に相当します。
そのためここでは、真鍮の「応力除去焼きなまし」の効果を考えてみたいと思います。
(1)真鍮の加工硬化
どんな金属にも言えることですが、何らかの力を加えて加工すると、その金属を構成している原子の並びにひずみが生じ、元に戻りにくくなります。その結果、その部分が固くなることを「加工硬化」と呼び、加えた力を「応力」、金属内に残ってしまった応力を「残留応力」と呼びます。マウスピースを加工する際にも、切ったり削ったり叩いたりという「加工」を施すわけですから、完成したマウスピースにも、当然のことながら「残留応力」が生じていることになります。そもそも、材料になる真鍮の棒(丸棒と言います)を作るとき、溶けた真鍮を丸い穴に押し通して作りますので、この時点ですでに「残留応力」が生じてしまいます。
まあ簡単に言うと、マウスピースの素材全体に、金属原子のムラがある状態です。
このムラを、そもそもの真鍮本来の状態に近づけるのが「応力除去」作業であり、その方法が「応力除去焼きなまし」と呼ばれます。
次では、この真鍮の「焼きなまし」方法、つまり「音響処理」方法について、紹介していきます。
(2)真鍮の「応力除去焼きなまし」=マウスピースや金管楽器の「音響処理」
真鍮の残留応力の変化については、浅枝敏夫氏、西本廉氏によって1958.2.7に発表されたこちらの論文に記されています。読むのが面倒な人は、論文中の「図4」だけご覧ください。これを見ると、残留応力は120℃を超えるあたりから減少し始め、300℃以上に熱すると、ほぼ0(ゼロ)になることがわかります。また加熱時間は30分と書いてありますので、
音響処理と呼ばれる熱処理は、
300℃程度以上の温度で30分以上加熱する作業
と考えることができます。自宅用の高性能のオーブンや、七宝焼きの電気窯などで、自分でもできるはず・・・
(3)その他の知識
①真鍮は銅と亜鉛の合金ですが、亜鉛の方が融点が低いため、加熱しすぎると亜鉛が真鍮から気化してしまい、表面が赤く変色(銅の色)してしまいます。ネット上では真鍮の焼きなまし温度について、「表面が赤くなる程度に熱して」等の表現も見られますが、「焼きなまし」の目的が「音響処理」であり、マウスピースや楽器の材料でもあることを考慮すると、300℃前後が望ましいと考えられます。
②アクセサリーの材料として真鍮を用い、その加工をしやすくするために「焼きなまし」をしている人は、加熱後に急速冷却(水に入れる)しています。これは焼きなましの目的が、材料を「柔らかく加工しやすい物にすること」であるためです。真鍮をゆっくり(空気中に放置)冷却すると、「時硬効果」という現象が起こり、せっかく柔らかくなった材料が少しだけ硬くなってしまうのです。でも鉄に焼き入れをするほど硬くなるわけではなく、真鍮が加熱によって「本来の真鍮の硬さ」に戻るだけで、金属原子を均一化させるという本来の目的(応力除去=音響効果)は果たしているため、音響処理としては、加熱後に空気中でゆっくり冷やすだけで問題はないはずです。
③(2)で紹介したグラフからもう1つ分かることは、加熱によって応力除去を行うと、真鍮そのもの硬度が低下する(柔らかくなる)という事です。マウスピースや金管楽器の材料という観点から考えると、「材料が柔らかくなる=響きを伝えにくくなる」とも言えますから、アクセサリー製作時のように、加熱後に急速冷却しない方が硬度が落ちず、響きが(本来の真鍮レベルで)保たれるという事にもなります。
そのうえ、金属原子が均等になることで、真鍮自体が「均等に響く」ようになるわけですから、この「真鍮の熱変性=音響処理」と呼んでも、問題はないと考えます。
④金属の熱処理には、「低音処理」もあります(サブゼロ処理、クライオ処理等)。これは鉄や鋼には有効ですが、真鍮への影響はほぼないと考えられます(金属中に炭素原子をほとんど含まないため)
(4)音響処理のまとめ
①「音響処理」なんて効果があるのか?とおっしゃる方もいるようですが、漠然と否定したり疑ったりするのは、格好の悪いことです。まずは、なぜ「音響処理」というものが注目されているのか、このサイトを読んで理解してみましょう。そして、300℃は無理でも、自宅のオーブンやオーブントースターで220℃ぐらいの状態は作れますから、自分で試してみてください。何なら、ガスレンジに網でも乗せてその上で焼いてみても・・・。もちろん、その結果や実験後のマウスピースの状態、火傷等の怪我には一切責任は持てませんけど。
②この内容をまとめるに当たり、自分でも音響処理という名の熱処理を、マウスピースと仏壇用の鐘に施してみました。マウスピースの方は、処理前に比べ、音域による音ムラ(鳴る音と鳴らない音の差)が少なくなったような気がしました。音響処理をすると「音に響きが増す」等の記述を目にすることがありますが、その点については実感できませんでした。
1つ言えるのは、間違いなく「変化」はあります!
ただその変化が、「マウスピース等の違いによる変化は、進化?退化?」の所で前述しましたように、その人にとって好ましい変化であるのか、そうでないのかの確率は、50%:50%です!
|